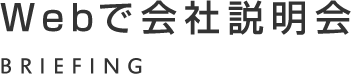- 株式会社メディックメディア TOP
- Webで会社説明会
- メディックメディアってどんな会社?
- 読者参加型の本づくり
読者参加型の本づくり
いつも社内に読者がいる環境
次は、「読者参加型の本づくり」について話します。
読者の意見を聞く、ニーズをとらえるといえば、よくある表現ですが、代表・岡庭の行った方法は、座談会やインタビューといった生半可なマーケティング手法にとどまりません。
読者代表である医学生を、人件費をかけてアルバイトとして雇用してしまう。
例えば、執筆者から届いた原稿がどうしたらもっと良くなるか、それこそ1ページ1ページ、1行1行を具体的に吟味してもらいます。
そして、よりわかりやすくするためのアイデアを練り、ドクターに提案するのです。この方法が社内に浸透し、システムとして確立していったのです。
現在は医学生の方だけでなく、医師、看護師、看護学生の方もいらっしゃいますので、アルバイトの総数は相当な数にのぼります。
その分コストもかかりますが、そこまで徹底して具体的に読者のニーズをとらえようとするから、小社の本は、読者に拡がっていき、トップシェアを確立でき、かけたコスト以上の効果をあげることができているのです。
つまり、楽に結果を出せる方法はなく、かけるべきポイントにコストと労力をかけることでシェアを伸ばす。それが「読者の視点を徹底していられる」という方法論なのです。
ちなみに、この「学生バイト」の方々は、医学や看護などを教えてくれる家庭教師であると同時に、共に苦労した仲間でもあるので、バイトを卒業した後も、彼らと友人として長く付き合っていく編集者も多いです。

おしゃれな街(のはず)、青山で地味~に、しかし熱く、原稿を吟味してくれる医学生たち

でも素のときは、いたって普通の明るい好青年たちです。
読者ニーズをとらえた確信があるから
3つ目のポイントは、「常識に縛られない」こと。
例えば、『病気がみえる』。多方面から「ターゲットを絞らなくては本は売れない」と言われる中、代表・岡庭は、あえて読者層を限定せず“チーム医療を担う医療人共通のテキスト”として本書を企画しました。
その制作方法は、イラストレーターを外注でなく社員採用し、相当な経費をかけてつくるというもの。
しかも苦労してコストをかけて完成させた本は、医学教科書としては超低価格の設定で発売しました。
こうした要素は全て、それまでの常識では考えられないものでした。
他社や書店からみればかなり無謀に思えたこの企画は、立ち上げ当初は苦しんだものの、結果的には、実際に職種の壁を越えて、医学書総合ランキング上位を独占する勢いでヒット。
毎年部数が落ちずに売れ続け、良い利益を出せるシリーズに成長しました。
なぜできたか?それは、「医学は難しい…徹底的にビジュアルで理解できる本が欲しい」という読者のニーズをとらえ、それに応えることができれば必ずヒットし、コストがかかっていても必ず利益を出すことができるという確信が小社にあったからなのです。
つまり、「常識に縛られない」の発想の上流には「読者ニーズをとらえた確信」がある。単なる「非常識」ではないということです。
そして、このような発想で企画された本が、すべて小社の主力商品になっています。
この発想が、そのままメディックメディアの編集スタイルになっています。
編集者が編集の根幹を担い、読者の反応をみながら試行錯誤できる――。
この仕組みが、「常識に縛られず」チャレンジできる環境をつくってくれているのです。
日販医書センター 医学書総合ランキング 2023年間ベスト100(2022年12月~2023年11月)
- 順位
- 出版社
- 書名
- 1
- 南江堂
- 今日の治療薬 2023
- 2
- 文光堂
- 糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版
- 3
- 文光堂
- 糖尿病治療ガイド 2022-2023
- 4
- メディックメディア
- クエスチョン・バンクSelect必修 2023-24
- 5
- メディックメディア
- 看護師・看護学生のためのレビューブック 2023-24
- 6
- 金原出版
- 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2023年版
- 7
- メディックメディア
- クエスチョン・バンク看護師国家試験問題解説 2023-24
- 8
- 医学書院
- 内科レジデントの鉄則 第4版
- 9
- ナツメ社
- これならわかる!心電図の読み方
- 10
- 医学書院
- 医療者のスライドデザイン
- 11
- 中央法規出版
- ケアマネジャー試験ワークブック 2023
- 12
- メディックメディア
- からだがみえる 第1版
- 13
- 照林社
- 看護学生クイックノート 第3版
- 14
- メディックメディア
- 病気がみえる vol.2 循環器
- 15
- メディックメディア
- 病気がみえる vol.15 小児科
- 16
- 医学書院
- 京都ERポケットブック 第2版
- 17
- 南江堂
- Essential細胞生物学 原書第5版
- 18
- メディックメディア
- 病気がみえる vol.7 脳・神経
- 19
- 医学書院
- ナースポケットマニュアル
- 20
- 医学書院
- PT・OT・STのための臨床5年目までに知っておきたい予後予測の考え方
- 21
- メディックメディア
- 病気がみえる vol.1 消化器
- 22
- ナツメ社
- これならわかる!人工呼吸器の使い方
- 23
- メディックメディア
- 病気がみえる vol.11 運動器・整形外科
- 24
- 医学書院
- 医学書院看護師国家試験問題集 2024年版
- 25
- 医学書院
- 治療薬マニュアル 2023
- 26
- 医学書院
- 子どものための精神医学
- 27
- 照林社
- ズボラな学生の看護実習本 ずぼかん
- 28
- 南江堂
- 糖尿病治療の手びき 2023
- 29
- 中央法規出版
- ケアマネジャー試験過去問解説集 2023
- 30
- 照林社
- 病棟でよく使われる「くすり」ポケット事典
(出典:医学書出版情報2023年12月 No.465/受注ベース)
『病気がみえる』は医学書総合ランキングでも上位を占める大ヒットに。