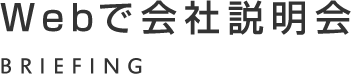- 株式会社メディックメディア TOP
- Webで会社説明会
- メディックメディアってどんな会社?
- 編集者が主役になる本づくり
編集者が主役になる本づくり
医学書編集は、読者視点を持ちにくい?
まず医学書の編集者の仕事が一般的にはどういうものか、それに対してメディックメディアの編集者の仕事がどういうものかを説明したいと思います。
医学書の編集はときに「小僧さん」のような仕事だといわれることがあります。これはどういう意味だと思いますか?
一般書籍の編集者の仕事は、比較的自分が読者視点を持ちやすいために、「自分で企画を立てやすい(実際に売れるかどうかは別ですが)」、「原稿の内容を編集者が理解できる、またはしやすい」、「原稿の改善点などを著者にアドバイスしやすい」ケースが多いと思います。
それに対して、一般的な医学書の編集者の場合、医学が専門的な内容であるが故に、読者の視点を持つことが難しく、「原稿の内容を理解しにくい」、「原稿の改善点などを著者にアドバイスしにくい」、「自分で企画を立てにくい」ケースが多いといえます。
編集者が文系出身でも理系出身でも同様です。
このため、通常の医学書出版社では、原稿執筆だけでなく企画や執筆陣の決定といった「編集」の根幹作業もドクターに依頼し、編集者は、スケジュールを立てたり、原稿を催促したりと、そのサポート役を行うことが多いのです。
つまり一般的な医学書の編集者の仕事は、「実務担当者」というイメージに近いのです。
進行管理などの実務はとても重要。でもそれだけでは仕事は面白くならない。
1ページ1行の表現まで積極的に関わる
しかし、そういう一般的な、常識的な方法で、小社ならではの個性をもった「新しい本」を作るのは限界がありました。
ドクターや看護師の方々は医療のプロであって本づくりのプロではないからです。
論文のような形式で医学を解説することは可能でも、「わかりやすく、使いやすい本」を創意工夫をこらしてつくるのは得意ではないことが多いのです。
仮に得意であったとしても、日々、臨床や研究で非常に多忙で、まとまった量のものを執筆する余裕はほとんどありません。
小社は医学書業界のなかでは、まだまだ新しい出版社。
他社の真似ではなく、「新しい医学書」をつくっていかなくては、成長できません。
ですから、私たちは、今までにない医学書制作を行うため、編集者がドクター・医学生・看護師らとチームを組み、「編集」に積極的に関わって本を作っていく方法を取るようになっていったのです。
その一例が『病気がみえる』。図版を考案し掲載するその量が圧倒的であるため、臨床で忙しい医師だけでは、実質的にはできません。
このため編集部内で編集者が、社員の医師や、アルバイトの医師・医学生とチームを作って図案のアイディアの大半を考えています。詳細は、『病気がみえる』についてをご覧ください。
他の本、たとえば問題集であっても、読者代表の学生らと内容を徹底的に吟味して作っていきます。
こういう感じなので、小社では、読者のニーズを自然につかみ、企画から1ページ1ページの内容にまで深く原稿に関わろうとする、そういう編集者が育つ環境ができていったように思います。
「医学をわかりやすくする」仕事だから
ここで重要になるのが、私たちが「医療系の学生向け」の出版をコアにしているということです。
専門医向けのコンテンツで「内容に踏みこむ作り方」を徹底するのは困難です。現場で働くプロでしか分からない要素が多く、情報の更新も早いからです。
でも、学生向けに「医学の基本をもっとわかりやすくする」仕事であれば、難易度は下がります。編集者は、教科書や論文を読むなどの自分の努力と医学生の方々や医師や看護師の先生方のサポート次第で、一定のレベルまでは踏み込めるようになり、幅広く活躍しやすいのです。(編集と学生だけで原稿を作るということはありません。専門の執筆者がいるか、監修という指導役がつきます)
結果的に、メディックメディアの編集者の場合、執筆者や監修者の先生方とともに、企画段階から、原稿の1ページ1ページの内容や表現の仕方、販売促進まで、徹底的にこだわることができるので「小僧さん」ではなく「主役」という感覚で仕事をするようになります。
それは必ずしも良いことばかりではありません。
努力が必要だし、産みの苦しみは大きい。人のせいにできない。1冊に関わる度合いが深くなるから出版点数も増やしにくい。
でも、そこまでやるから売れるようになります。そして売れるからどんどん仕事が面白くなる。面白いからがんばれる…。
不況に強い反面、成長率も高くはない医学書業界で、何故メディックメディアの本が医学書ランキングの上位を占め、毎年成長を続けているのか。
その答えの1つが「メディックメディアの編集者は小僧さんではない」ことにあると考えます。
栄養学生向けの問題集を制作中。問題集は一見地味に思えますが、学生が一番熱心に食いついてくれるので、編集者もがんばってしまうという実は熱いシゴト。